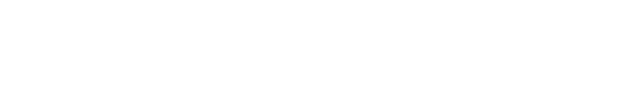ドクターコラム
年1回の健康診断に関して
おうちのドクター院長の黒澤秀章(くろさわひであき)です。
今回は、
書かせていただきます。
『健康診断と言われても、
病院やクリニックに通っているから、
健康診断は受けなくても、大丈夫じゃないの??』
と、よく患者さんから御意見をいただきます。
例えば、
糖尿病患者さんは、毎回採血と検尿を受けていただいておりますので、
確かに採血と検尿で把握できる異常に関しては、
日々確認することは出来ます。
しかし、
健康診断には、採血と検尿以外に、
心電図や、胸部レントゲン、便潜血などの検査も含まれていることがあります。
心電図で、不整脈や、狭心症などが見つかったり、
胸部レントゲンで、肺がんが見つかったり、
便潜血で、大腸がんが見つかったり
することもあります。
そのため、当院通院中の患者様には、
年1回は、会社での健康診断、もしくは、区役所からの健康診断を受けていただく様に、
説明をしております。
もちろん、
当院でも健康診断の対応をしております。
事前予約制となりますので、
是非お気軽にお問い合わせください。
当院は、
どの時間帯でも糖尿病専門医が診察対応致しますので、
健康診断の結果などで、
血糖値でご心配なことがありましたら、
おうちのドクター院長 黒澤秀章
「ダイエット外来もやっています♪」
こんにちは🌸
もともと民放のテレビドラマはリアルタイムで観るほうではないのですが、わたしのなかで今期イチオシなドラマが、テレ東の「ディアマイベイビー」✨️
松下由樹さんの突き抜けた怪演ぶりや、ドラマの演出や構成がテレ東ならではというか、非常に独創的で、ぜひおすすめのドラマです♪
さて、今日はダイエットのお話をしようと思います。
当院にはダイエットのご相談で来院される患者様も来院されますが、やはり多くの方は
薬剤治療に対しての関心が高いようです。
現状ダイエット治療薬として当院で提案薬剤は、大きくわけて3種類あります。
→
【サノレックス】
厚生労働省が認可した日本初の食欲抑制剤
脳に直接働きかけて満腹中枢を刺激し食欲抑制効果をもたらす
一方で依存性形成等の副作用が懸念される薬剤でもあり、服用期間は3カ月間に限定されている
【ゼニカル】
オルリスタットという有効成分によって、体内の脂肪の分解・吸収が一部抑制される
吸収されなかった脂肪は便中に排泄されるため、消化器症状やビタミン欠乏等の副作用が起きる可能性がある
【GLP-1作動薬】
*糖尿病治療薬であり、原則糖尿病患者さんが対象
GLP-1は、食事摂取により小腸から分泌されるホルモンの一種で、インスリン分泌を
促進し血糖を下げるだけではなく、胃の動きを遅らせることで満腹感を持続させたり、
脳内の受容体に作用することで食欲を抑制し、減量効果が期待できる薬剤
近年では一部の薬剤に関しては、糖尿病がなくても高度肥満患者に限り「肥満治療薬」
として保険適用で処方可能となったが、処方できる医療機関は教育認定施設のみ
ただこれらの薬剤を服用したとしても、やはり基本の食事療法や運動療法なくしては、
持続しての減量は難しいのだと、患者さんを診ていて日々実感しております。
薬効や副作用の程度に関しては本当に個人差がありますし、服薬当初効果が得られたと
しても続けていくうちに身体が慣れていき、効果を実感しづらくなってリバウンドをしてしまう方も多かったりします。
また、食欲が過剰で自制が難しい方の中には、単なる大食漢ではなく、睡眠障害、ストレス等によるメンタルの不調が大きく関連し、そちらへの介入がまずは必要だったり、稀ではありますが、内分泌疾患が潜在していることもありますので、表面的な診察ではなく、私たちが患者さんそれぞれのバックグラウンドや身体的・精神的状態を知ることがダイエット外来において一番重要だと感じております。
ところで、朝ご飯って食べていますか?
朝食抜きという方けっこう多いようです。
欠食の理由としては、夕食時間が遅くて朝お腹が空かない、、、、食事の支度をするのが面倒、、、もともと食べない習慣だから、、、、etc。
朝食を抜くことは、昼夜の過食や血糖変動、代謝低下を引き起こし、ゆくゆくは生活習慣病のリスクを上昇させるともいわれています。
起床して2時間以内に(遅くとも10時までに)食事をすることで、体内時計がリセットされ、ホルモン分泌や自律神経が適切に調整され、代謝も上がるため、
朝食は健康維持にとても大切なのです。
当院では4月より、食事サポートの一環としてフォーミュラ食品【オベキュア】の取り扱いを始めました。
フォーミュラ食とは、糖質・脂質を必要最小限に抑え、蛋白質・ビタミン・ミネラルを必要十分量含む低カロリーの栄養食品で、臨床の場では、肥満患者さんに対してのVLCD療法(1日の摂取カロリーを大幅に制限し、短期間での減量を目指す方法)で導入されています。
市販の製品も様々あるなかで、【オベキュア】は医療機関のみで購入可能な食品です!
大豆タンパクを主成分とし、各種ビタミン、葉酸、ミネラル等必要な栄養素が含まれて
おり、食事の置き換えにより減量効果が期待できます。
また、タンパク質は他の栄養素と較べて消化吸収の過程で消費されるエネルギー量が
多く、摂取することで代謝量が上がるため、朝食での置き換えが最も減量に有効です。
フレーバーも5種類あり、けっこうおいしくて、あまいものがお好きな方であれば
無理なく続けられると思います。
朝ごはんにオベキュア、ぜひ試して下さい♥
おうちのドクター医師 田中紗代子
過去記事はこちらか
●2025年4月2日「あのワクチンも定期接種へ!」(田中先生)
●2025年3月31日「さんちゃ会」第3弾に関して(黒澤先生)
●2025年2月26日 「女子の大敵 膀胱炎!」(田中先生)
●2025年2月12日 日本総合健診医学会 第53回大会のシンポジウムにて発表させていただきました(黒澤先生)
●2025年1月22日 「胃腸、つかれてませんか?」(田中先生)
●2025年1月9日 「地域医療における当院の役割に関して」(黒澤先生)
●2024年11月6日 「ワクチン接種で冬支度」(田中医師)
●2024年10月29日 甲状腺とは ~その4(甲状腺の主な抗体検査)~(竹尾医師)
●2024年10月23日 糖尿病患者さんのかかりつけ医としての役割に関して(黒澤医師)
●2024年10月2日 「血糖の乱高下で悩んでいるあなたへ)(田中医師)
●2024年9月25日 甲状腺とは ~その3(甲状腺の主な検査)~(竹尾医師)
●2024年9月18日 糖尿病患者さんの採血と食後高血糖に関して(黒澤医師)
●2024年8月27日 「食後のだるさは●●●が原因だった・・・?)(田中医師)
●2024年8月21日 甲状腺とは ~その2(甲状腺の主な病気)~(竹尾医師)
●2024年8月7日 糖尿病患者さんの血糖値に関して ~高血糖と低血糖~(黒澤医師)