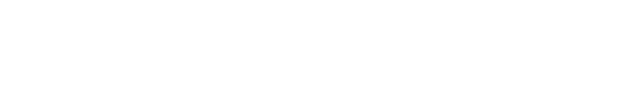「とある日の症例から」
こんにちは🌸
お盆休みもあっという間に終わってしまいました😢😢😢
残暑に加え、まだまだ日常モードに身体がついていかず、バテてしまっている方も
多いと思いますが、お互いなるべく気を楽にゆるくがんばりましょう🍑
日々の診療のなかで「これで大丈夫だったかな」と不安になったり、「なんでわたしこんなこと気づかなかったんだろう」と頭を抱えたりすることって未だにあり、やはりこの医師という仕事は一生勉強なのだと思います。
今回は、最近私が経験したある症例について(自身への戒めも込めて…)のお話です。
患者さんは50代の男性の方で、定期通院されている2型糖尿病、アルコール性肝障害の方です。
多忙のため長らくオンライン診療対応でしたが、体調不良で半年ぶりに当院を受診されました。
自覚症状は、数週間前に転倒して以降続いている両足のむくみと打撲痛、気力低下、疲労感でした。
もともと肌艶もよく背筋もぴしっと若々しい方でしたが、来院時は顔色不良、頬もこけて両足は非常にむくみ、すこしふらふらした様子。
目に力はなく、どことなくぼんやりしており、以前とは激変された印象でした。
この数か月間、ストレスにより、飲酒量が増え、食事も連日お寿司ばかりと
かなり生活が乱れていたとのこと。
やつれているのに関わらず、体重は前回受診時より数キロ増加、以前はなかった尿蛋白が出現していました。
一方不規則な食生活をしていた割にHbA1c値は良好でしたが、眼瞼結膜が蒼白であり、貧血による影響で低下していると思われました。
診察上、明らかな筋力低下や麻痺等神経所見の異常は認めませんでした。
うつ、何らかの腎炎、悪性腫瘍、硬膜下血腫等の可能性を検討しましたが、当初は糖尿関連の検査結果しかでておらず、とにかく早急に塩分制限やビタミン摂取等食生活の改善を促し、利尿剤を一旦処方し、数日後の受診としました。
そして再診時。
野菜を食べるようになり飲酒量も減らしているとのことで、体調はだいぶ回復されたご様子でした。
血液検査では、アルブミン(タンパクの一種、栄養状態の指標ともされる)やヘモグロビン(貧血の指標)の低下が目立ち、他項目に大きな異常は認めませんでした。
ご本人の改善した状態とも併せて、なにか重大な疾患が潜在している可能性は低いと考えましたが、他院へ画像精査いただくこととしました。
そして紹介先の医療機関より報告書が届き、診断はなんと「脚気」。
脚気は、江戸~明治期、多くの死者を出した国民病として知られています。
特に軍人間では、戦死者よりも脚気での死亡者が多いと言われたくらい深刻な状態でした。
当初は感染症とされていましたが、のちに精白米の多量摂取によるビタミンB1不足との
関連が明らかになり、食生活の大幅な改善で以降脚気は激減した、、、、
はずでした。
しかし近年、高齢者社会や「引きこもり」増加により孤食が増え、簡単に用意できる
インスタントラーメン等の偏った食生活により、脚気の潜在患者さんがひそかにふえているようです。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換したり、細胞修復や神経の情報伝達に働くなど
私たちの体内で非常に重要な働きを担っており、シリアルや豚肉、麦飯、玄米、野菜等に
多く含まれています。
欠乏が数カ月続くと、心不全(脚気心)や手足のしびれ(末梢神経炎)、また中枢神経に影響がおよぶと意識障害、認知機能障害等(ウェルニッケ脳症)等様々な症状が出現します。
よって長期食事がとれない入院患者さんや悪阻がひどい妊婦さんとかには、あらかじめ予防でビタミンB1を点滴投与したりします。
ただ、食事が摂れていたとしてもその状況次第では、この現代においても、脚気発症のリスクがあることはわたしにとって全くの盲点でした…
炭水化物やアルコールの多量摂取、ストレスフルな環境等は、糖代謝を過剰に促進し、結果ビタミンB1の消耗やエネルギー不足につながるといわれています。
今回の症例はまさにいずれも該当しており、症状や生活背景から、
早い段階でビタミンB1欠乏を疑い投薬を行うべきだったと痛感しました。
日本での最近の症例報告では、難治性の下肢潰瘍の精査の過程で、生活背景の詳細な聴取により脚気との関連が判明した独居の高齢者や、若年のひきこもり患者のウェルニッケ脳症発症例が掲載されておりました。
脚気は決して昔の病気ではなく、むしろ飽食、ストレス、人との関わりが希薄な現代社会だからこそ、さらにはその多彩な症状ゆえに、鑑別のひとつとして常に留意しなければいけないことを改めて認識しました。
幸いにも前述した当院の患者さんは軽症にとどまり、ビタミンB1処方にてみるみる回復し他県に転居されていきました。
今回はわたしにとって非常に教訓となった症例を経験しましたので、ここでご紹介とさせていただきました。
ではこのへんで😊
おうちのドクター医師 田中紗代子