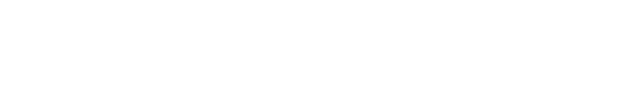[もしもたんぱく尿が出たら、]
こんにちは🌸
ようやく長く続いた残暑もようやくおさまり、ようやく秋の気配が濃く感じられるようになってきました🍡
わたしは柔軟剤フリークで常に数種類くらいの柔軟剤を常備しているのですが、秋の夜半洗濯物を干すとき心地よい夜風に乗ってふわーっと香るのが何気に幸せです😊
さて、本日はたんぱく尿のお話です。
普段通院する習慣のない健康な方でも、これまで一度は学校や職場の健診で尿検査を受けたことがあるかと思います。
時々あるのが、「健診でたんぱく尿がでた」とのご相談。
通常は、腎臓のなかの血液を濾すフィルターの役割を担う糸球体、濾過後の原尿から必要な物質を再吸収する尿細管のおかげで、微量こそあれ、まとまった量の蛋白が尿中に漏れ出ることはほとんどありません。
まずたんぱく尿がでたら、採尿をした時の状況や体調、また高血圧症や糖尿病などの病気がないか、尿中に他に異常所見がないか、を調べることが重要です。
健診や外来で広く行われている尿検査は、試験紙を用いた簡易な蛋白定性試験であり、±→15mg/dl、1+→30mg/dl、2+→100mg/dl、3+→300mg/dlの蛋白が検出されることをそれぞれ意味しています。(ちなみに臨床的なたんぱく尿とは、1日のなかで150mg以上の蛋白が尿に排泄されることを指します。)
たんぱく尿はざっくりわけると、生理的蛋白尿と病的蛋白尿の2つに分類されます。
前者は特に腎・尿路に病変がない、つまり病的意義がないタイプ。
例えば、痩せ型の思春期の学生さんに多くみられるのが起立性蛋白尿。
起床後体を動かすことで腎臓の血流量が変化し、糸球体が圧迫された結果たんぱく尿を認めるケースです。
活動開始後の採尿ではたんぱく尿を認める一方で、朝一番の採尿では検出されないことが診断の決め手になります。
その他、激しい運動や感染、入浴後、ストレス、月経や性行為も生理的蛋白尿の要因となりますし、尿定性検査では検体尿の濃さも結果に影響します。
病的蛋白尿の場合、腎前性(糖尿病、心不全や甲状腺疾患など腎臓以外の臓器障害)、腎性(糸球体、尿細管)、腎後性(尿管)のいずれかになんらかの疾患が潜在しているという重要なサインとなります。
その病態も緩徐なものから急激に進行するものまでさまざまです。
食事療法や血圧管理等で経過をみる症例もありますが、たとえば、糸球体の機能破綻により高度の尿蛋白と浮腫をきたす「ネフローゼ症候群」という病態では、急激に末期腎不全に移行することもあるため、早急な診断の上でステロイド剤や免疫抑制剤の投与が必要となります。
いずれにせよ、多量のたんぱく尿の持続はいずれ末期腎不全→透析療法へ移行する可能性や心血管疾患発症リスクと関連していることが報告されているため、早い段階でアプローチし進行を予防しなければなりません。
腎機能を示すクレアチニン値や尿蛋白量の変化の度合い、腎疾患の家族歴の有無等が
病態の予後を予測する上で重要なポイントになります。
腎機能が正常且つ治療中の病気もない方が+程度の蛋白尿をはじめて認めた場合、
再度早朝尿で検査し異常がなければ、一過性のものと考え特に心配する必要はありません!
一方、たとえ自覚症状がなくても、2+以上のたんぱく尿を認める、または継続してたんぱく尿を認める場合は、速やかに精査を行う必要があります。
精査とは、具体的にいうと、血液検査(腎機能や免疫系の異常、膠原病等がないか)、蛋白尿定量の測定(定性と違って尿濃度の影響を受けず蛋白量を測定できる)、尿沈査検査(血尿のもとである赤血球や、腎障害を反映する円柱所見がないかを確認)、超音波検査(腎臓のサイズや形態を顕微鏡で確認)、また的確な診断・治療のために腎生検が必要になることもあります。
たんぱく尿がでたら、まずは医療機関受診を!!!
おうちのドクター医師 田中紗代子